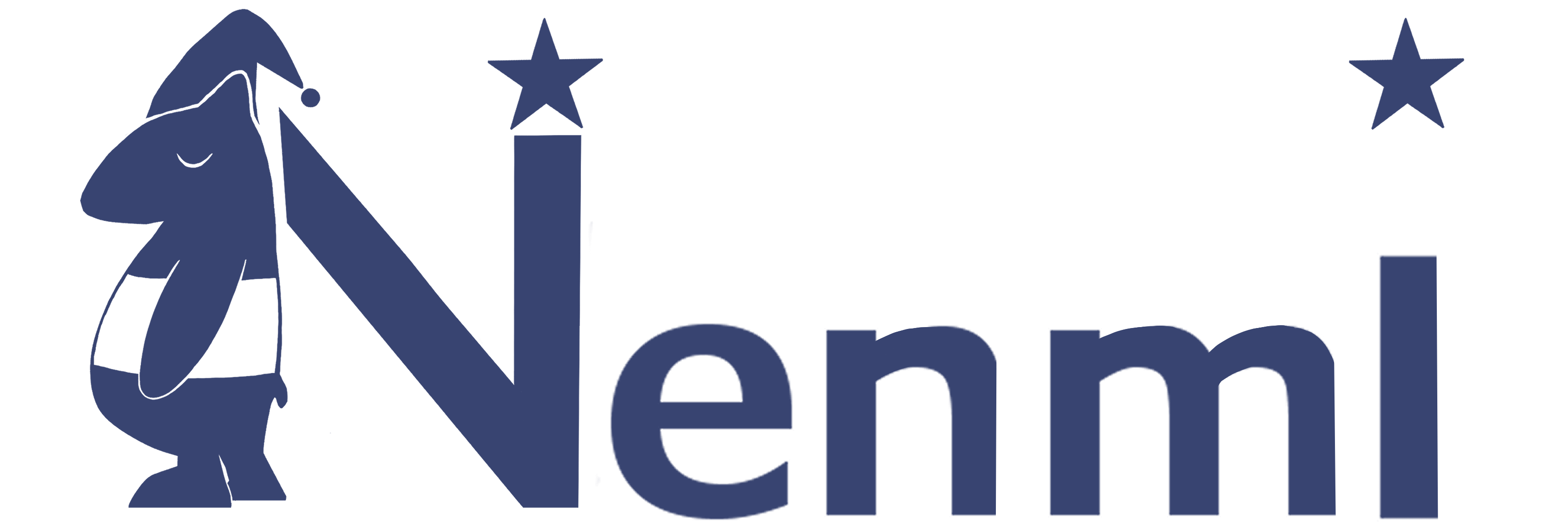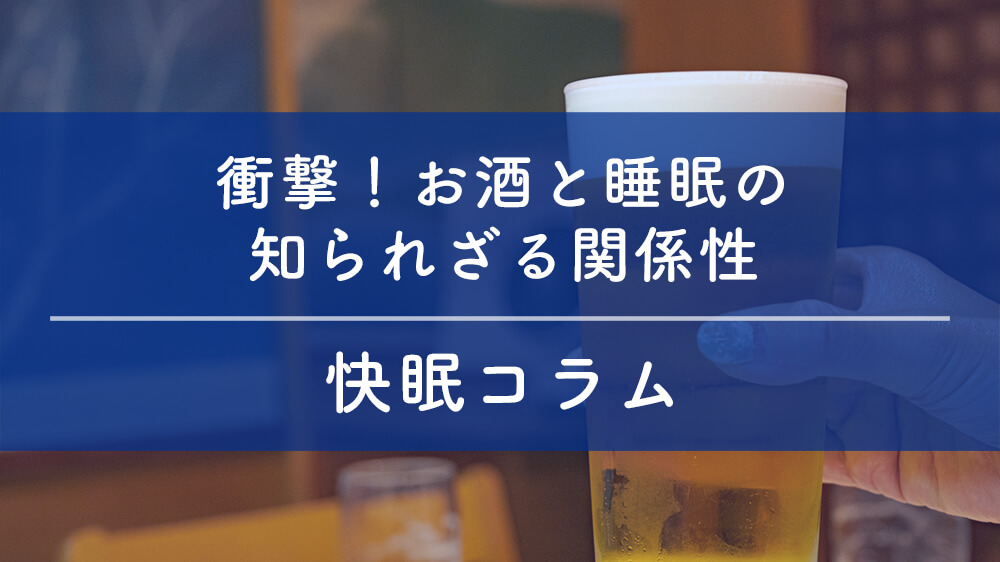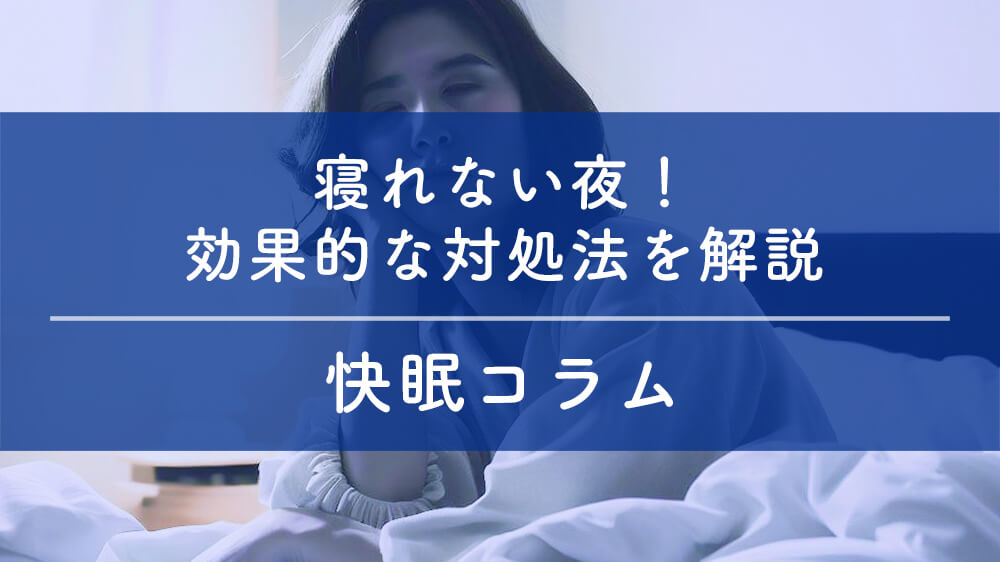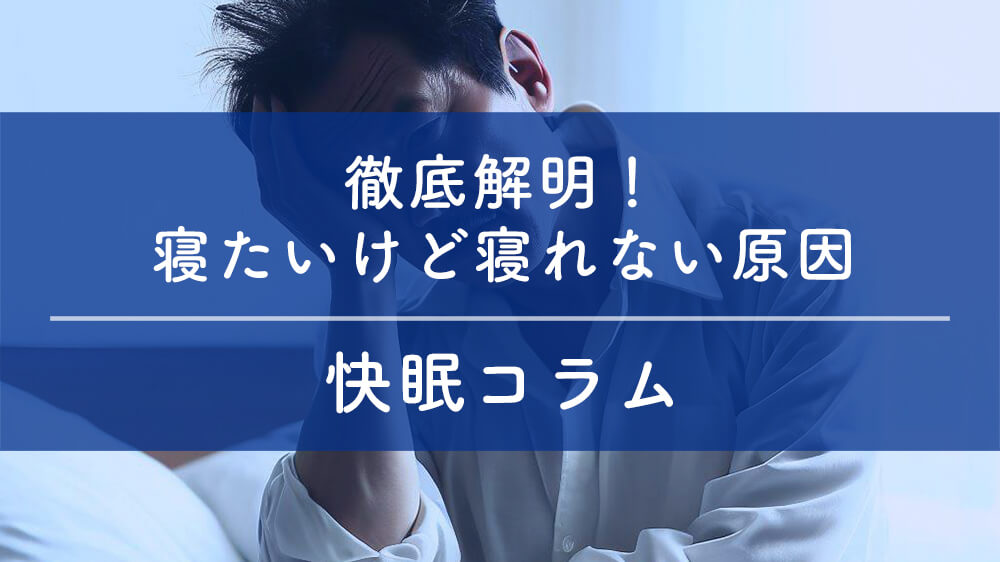- 睡眠とアルコールの関係性の理解
- お酒による睡眠障害の可能性
- 正しくアルコールと向き合う方法

最近睡眠の質を上げるためにお酒を控えてたんだけど、
どうしても断れない飲み会に誘われちゃったんだ。

お酒を控えることは健康にいいですが、
お付き合いのお酒の場は外せないこともありますよね。

そうなんだよ〜!これだけ控えていたのに
お酒を飲んでも大丈夫なのかな?

飲み過ぎは良くないですが、時と場合によっては飲んでも大丈夫です。

それでは今回は、お酒と睡眠の関係について詳しく知り、
正しいアルコールとの向き合い方を学びましょう。
- お酒を飲みたいけれど、睡眠に影響がないか心配
- お酒をどの量、どのくらい飲むべきかわからない
- お酒で眠りやすくなるが、睡眠の質を下げる
- 飲酒は深刻な睡眠障害を引き起こす可能性がある
- お酒には飲むべき量、タイミング、種類がある
睡眠とお酒の関係性

皆さんはよくお酒を飲むでしょうか?一人で嗜むのが好きな人もいれば、家族や友達とワイワイ食と共にお酒を楽しむ人、または仕事の付き合いで一緒に盃を交わす人もいますよね。お酒の楽しみ方、付き合い方は人それぞれですが、健康面が気になる方も多いのではないでしょうか?実際にこれまでお酒に関しては様々な実験や研究(https://www.arukenkyo.or.jp/book/all/pdf_nr/nr_23_01.pdf)が行われ、新たな事実が次々と明らかになっています。
中でもお酒と睡眠の関係性については、沢山の研究を通して色々な議論が巻き起こっています。この章では、お酒を飲むことにより睡眠に起こりうる影響を紹介していきます。
お酒が睡眠に与えうる影響
眠気の発生
お酒には神経系を麻痺させるという作用があり、これにより神経細胞の活動が鎮静化します。また同時に神経系を鎮静化するGABAと呼ばれる脳内の神経伝達物質の働きが促進されます。これらの鎮静作用により脳の活動が抑制され、人は眠気やリラックス感を感じることがあるのです。
また頭痛や吐き気を催すとも言われるアセトアルデヒドはアルコールの分解により生成され、分解酵素を上手くはたらかせることのできない体質を持つ人はこのアセトアルデヒドが血液中にたまりやすいため少ないアルコール量でも眠気を感じやすくなります。
しかしこのような眠気は、深い眠りにつながるとは限られません。むしろ、浅い眠りが誘発され夜中に途中で目が覚めてしまうことがあります。
眠りの質の低下
- メラニンの分泌の妨害
- ノンレム睡眠・レム睡眠の妨げ
- 体温の低下
- 利尿作用
また、お酒を飲むことで体温が下がる傾向があります。そのためお酒を飲んだ後に寒さを感じやすくなり、このような体温が下がった状態で眠ることで、深い眠りにつきにくくなる恐れがあります。
更には、お酒を飲むことで尿の量が増える傾向があり、夜中に何度もトイレのために起きてしまい、深い眠りにつながりにくくなります。
このようにお酒を飲むと眠気が誘発され眠りに入りやすくなりますが、結果的には睡眠の質が低下する恐れがあります。
睡眠時に望まれる回復度合いが下がる
飲酒をすると、アルコールによる利尿作用と代謝に必要な酸素不足により体内の水分が失われ、脱水症状を引き起こします。体内の代謝や体温調節に影響が及び、睡眠時の回復力の低下が懸念されます。
また、体内のアルコールが完全に代謝されるまでに時間がかかるために、アルコール中毒の人は、飲酒後は朝まで眠ることができないことがあります。
睡眠障害の可能性

睡眠時無呼吸症候群(SAS)
お酒を飲むと、喉や喉頭の筋肉が緩み、気道が狭くなることがあります。これにより、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を引き起こす可能性が高くなります。
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時に空気が通りにくくなることによって、睡眠中に呼吸が停止することが繰り返される病気のことです。主な症状としては、熟睡できない、夜中に何度も目が覚めてしまう、起床時に頭痛や倦怠感を感じる、昼間の眠気などがあります。
症状は深刻で、心血管系に影響を与えることがあります。一時的に自覚のできない呼吸停止が起きた際に、血液中の酸素濃度は低下し、心臓や脳などの臓器に供給すべき酸素が不足することがあります。このことにより高血圧、狭心症、脳卒中などの重い疾患を引き起こすリスクが高まります。
睡眠薬との併用はNG
お酒に含まれるアルコールには、中枢神経系を抑制する機能があるため、睡眠薬との併用は危険な副作用を引き起こすことがあります。
お酒と睡眠薬を同時に摂取することで肝臓の代謝が障害され、酩酊状態になりやすくなることに加えて薬の副作用があり、予期しない作用の組み合わせで異常が起こってしまいます。
実際に呼吸抑制や意識障害、死亡などが報告されているため、睡眠薬を服用している場合には、お酒は控えるべきです。
睡眠を重視する上でのお酒との正しい向き合い方

飲酒量
お酒を飲むと、その飲酒量によって睡眠に与える影響が異なります。
例えば少量のお酒であれば、先ほど述べたようにリラックス効果が期待できるため、眠りやすくなることがあります。しかし、大量のお酒を飲むと、血中のアルコール度が高まることで酩酊状態に陥り、眠りが浅くなったり、睡眠時無呼吸症候群を引き起こすことがあります。一般的には、1日に飲むお酒の量は男性で20グラム以下、女性で10グラム以下が好ましいとされています。
飲酒タイミング
お酒の飲みタイミングによっても、睡眠に与える影響が異なります。
例えば、夕食時や夕食後に飲むお酒は、胃の中で消化されるための十分な時間があり、アルコールが体内に行き渡るまでに時間がかかります。そのため、眠りにつく時間帯、あるいは眠りが深くなる時間帯にはすでにアルコールの効果がきれていることが多く、睡眠の質を低下させる確率が少ないとされています。
ただし、夜遅くに飲むお酒は、睡眠に与える影響が大きいため、控えることが望ましいと考えられるでしょう。
お酒の種類
驚くことにお酒の種類によっても睡眠に与える影響は異なります。以下に代表的なお酒の種類ごとに詳しく睡眠への影響を紹介します。
- ビール
- ワイン
- 日本酒
- ウイスキー
一般的にビールには、睡眠を誘発する効果があり、ビタミンB6やマグネシウムなどの成分が神経系の働きを安定させるさせ、リラックス効果を高めるため、寝つきが良くなりやすいとされています。
ワインの成分にあるレスベラトロールには、抗酸化作用があり、一般的に健康に良いと言われています。ところがワインに含まれるチラミンという成分は、興奮させる作用があるため、就寝前の大量摂取は寝つきを悪くします。
日本酒に含まれるアミノ酸のうち、リジンには、神経系を安定させる効果が特に多く見られ、リラックス効果があります。また、他のアルコールと比較するとアルコール度数が低く、適量を守れば睡眠の質への悪影響が少ないと考えられています。
ウイスキーには、睡眠を誘発する効果を持つアルコールが含まれていますが、アルコール度数が比較的高いため、飲みすぎは浅い眠りを誘発してしまいます。しかしテアニンというウイスキーに含まれている成分には、ストレス軽減効果とリラックス効果が期待できます。